おしりの粉瘤は自然に治らない。痛みや腫れがある人は早めに専門医へ

おしりは、座る・擦れる・蒸れるといった刺激が多く、粉瘤が悪化しやすい場所です。
痛みがなくても、しこりが徐々に大きくなっていたり、繰り返し同じ場所にできているなら、それは粉瘤の可能性があります。
自然に治ることはなく、放置すれば炎症を起こして腫れたり、膿が出たりすることもあります。
痛みが強くなってからでは手術も大がかりになるため、違和感の段階での受診が大切です。
この記事では、おしりにできる粉瘤の特徴、よく似た他の病気との違い、治療方法や手術費用、再発のことまで詳しく解説しています。
「病院に行くほどでもないかも…」と迷っている方ほど、ぜひ参考にしてください。
座ると痛い!おしりにできる粉瘤は2種類

粉瘤は症状のない「無症候性粉瘤」と痛みや腫れを伴った「炎症性粉瘤」に分類されます。初期段階ではほぼ痛みがなく気付かないため無症候性粉瘤の状態で進行し、何らかの影響で感染を起こすと炎症性粉瘤となり強い痛みや腫れを伴います。炎症が一度治ってもまた再発する事も少なくありません。
無症候性粉瘤

無症候性粉瘤とは、炎症や感染を起こしていない状態の粉瘤を指します。皮膚の下にコリッと硬いしこりのようなものが触れるのが特徴で、痛みや赤みなどの症状は見られず、ゆっくりと時間をかけて大きくなっていくのが一般的です。
おしりにできた場合は、歩行時や座ったときに違和感として初めて気づく方が多く、
「脂肪の塊かな」
「ニキビの芯があるのかな」
と自己判断してしまうケースも少なくありません。

粉瘤の中心には、毛穴のような小さな黒い点(開口部)が見えることがあり、これは皮膚の表面と粉瘤の袋がつながっている入り口です。開口部が見えないケースもありますが、この黒い点があれば粉瘤である可能性が高くなります。
炎症性粉瘤

炎症性粉瘤は、無症候性の粉瘤に細菌が入り込み、感染を起こした状態です。
それまで痛みもなく静かに存在していたしこりが、ある日突然赤く腫れ上がり、強い痛みや熱感を伴うようになるのが特徴です。患部に触れると熱を持っていたり、軽く触れただけでもズキズキと響くような痛みを感じたりすることもあります。

さらに進行すると、粉瘤内部に膿がたまり、皮膚が破れて中身が外に出てくることもあります。おしりにできた場合、膿が下着に染み出したり、座る動作が激痛を伴うなど、日常生活に大きな支障をきたす状態になります。
また、皮膚の奥で化膿が広がってしまうと、通常の切除よりも大きく切開して膿を排出する「切開排膿処置」が必要になるケースもあり、跡が残りやすくなる・治癒まで時間がかかるといったデメリットも考えられます。
おしりのできもの ― 粉瘤と間違えやすい他の疾患

おしりのしこりや腫れがすべて粉瘤とは限らず、類似する疾患も複数あります。以下のような病気との鑑別も重要です。
- 脂肪腫(リポーマ)
- 慢性膿皮症(化膿性汗腺炎)
- ニキビ(尋常性ざ瘡)
- せつ・よう
- 毛巣洞(もうそうどう)
脂肪腫(リポーマ)

脂肪腫(しぼうしゅ)とは、脂肪細胞が増殖してできる良性の腫瘍で、皮下脂肪層に柔らかいしこりとして現れます。
触るとやわらかく、弾力のある感触で、皮膚との境目が比較的はっきりしており、指で押すと少し動くのが特徴です。
脂肪細胞が増殖するだけなので基本的に痛みや赤みなどの炎症症状を起こす事はなく、時間をかけて少しずつ大きくなっていく傾向があります。おしりや背中、肩など脂肪の多い部位にできやすいとされており、数cm~10cm以上になることもあります。
脂肪腫は無症状であることが多いため、粉瘤や他の腫瘤と見分けがつきにくく、「なんとなくしこりがある」「押すと動くけど痛くない」といった症状だけで放置している方も少なくありません。
慢性膿皮症(化膿性汗腺炎)
慢性膿皮症(まんせいのうひしょう)は、毛穴や汗腺のある部分に慢性的な炎症や膿が繰り返し生じる原因不明の炎症性皮膚疾患で、特におしり・脇・鼠径部(そけいぶ)など、汗や摩擦が多い部位に発症しやすいのが特徴です。
症状としては、しこりのような腫れ・赤み・痛み・膿の排出などが現れ、何度も同じ場所に繰り返す傾向があります。一見すると粉瘤やニキビと似ているため、誤って粉瘤と診断されることも少なくありません。
慢性膿皮症は単なる一時的な皮膚炎ではなく、毛包の慢性的な閉塞と感染が関係しており、複数の膿胞や瘻孔(ろうこう:皮膚の下にトンネルのような管ができる状態)を形成することもあるため、進行すると皮膚が硬く盛り上がり、瘢痕(はんこん:傷あと)を残すこともあります。
この疾患は皮膚科でも対応され抗生物質の投与やステロイドを使用した治療が行われますが、皮膚自体が問題となるため、重症例では皮膚自体を切除して皮弁を使って覆ったり、植皮をして改善を計る場合もあります。専門的な治療が必要となることもあるため、粉瘤との見極めを含めて早期の正確な診断が重要です。
ニキビ(尋常性ざ瘡)
ニキビ(医学的には「尋常性ざ瘡(じんじょうせいざそう)」)は、皮脂の分泌が活発な部位で毛穴が詰まり、炎症を起こすことで発生する一般的な皮膚トラブルです。
おしりにできるニキビもその一種で、「おしりニキビ」などと呼ばれることがあります。
炎症を伴うこともありますが、一般的には赤みや軽い腫れが出る程度で、サイズは小さく、痛みも強くないことが多いのが特徴です。毛穴詰まりによる白ニキビや黒ニキビ、炎症性の赤ニキビなど、段階によって見た目が変化します。
ただし、繰り返しできる場合や、複数同時にできている場合、かゆみや膿を伴う場合には、粉瘤や化膿性汗腺炎など他の疾患と誤認されることもあります。見た目が似ているため、自己判断だけでは見分けが難しいこともあるのです。
せつ・よう
「せつ(癤)」や「よう(癰)」は、毛包や皮脂腺に細菌が感染して化膿し、炎症を起こす急性の皮膚感染症です。いずれも黄色ブドウ球菌などの常在菌が関与し、皮膚のバリアが弱まったときに発症しやすくなります。
「せつ」は、毛穴の奥にできる単一の膿のかたまりで、赤く腫れて押すと痛みを伴うことが多く、しばしば中心に白い膿がたまった膨らみが見られます。
これに対して「よう」は、複数の毛包にまたがって感染が広がり、いくつかの膿が皮膚の下で合体して、大きな腫れやしこりに発展した状態です。重症化すると発熱やリンパ節の腫れを伴うこともあり、抗生物質による治療や切開排膿が必要になるケースもあります。
毛巣洞(もうそうどう)
毛巣洞(もうそうどう)とは、おしりの割れ目(仙骨部)にできやすい慢性的な皮膚疾患で、体毛が皮膚の内部に入り込むことで異物反応や炎症が起こり、袋状の構造(嚢胞)や膿がたまりやすくなるのが特徴です。
10代後半~30代の若い男性に多く、長時間の座位・体毛が濃い・汗をかきやすい・蒸れやすい環境などが発症リスクを高めると考えられています。発症初期は赤く腫れて軽い痛みを伴う程度ですが、炎症を繰り返すと膿が排出される小さな穴(瘻孔)が複数できたり、皮膚の下にトンネル状の通路が形成されたりすることもあります。
粉瘤との違いは、中心に毛が混入していることが多く、炎症や膿が繰り返し起こる点です。ただし、見た目だけでは判別が難しく、粉瘤と誤診されることもあります。
おしりにできた粉瘤の見分け方

おしりにできたしこりや腫れが、粉瘤かどうかを判断するポイントは以下のとおりです。
皮膚の下にコリッとしたしこりがある
しこりは触れると動くことが多く、少し硬めの感触があります。
中央に黒い点(開口部)がある
毛穴のような小さな黒い点が見えることがあり、これが粉瘤の入り口です。
押すと白くて臭い内容物が出ることがある
中には皮脂や角質がたまっており、独特のにおいがします。
痛みはないが、徐々に大きくなっていく
初期は無症状でも、時間が経つと少しずつ大きくなるのが特徴です。
ただし、粉瘤と似た症状の病気も多く、自分で判断するのは難しい場合もあります。
正確に診断するには、皮膚や皮下の構造に詳しい専門医の診察が必要です。
「粉瘤かもしれない」と感じたら、なるべく早めに医療機関を受診しましょう。
おしりにできた粉瘤の治療法は手術が基本

おしりの粉瘤は自然に治ることはありません。また、潰して内容物を出しても、袋(嚢胞)が残っていれば何度でも再発します。
くりぬき法

くりぬき法は、粉瘤を小さな傷で取り除く治療法です。
専用の器具で粉瘤の中央に小さな穴を開け、そこから中の内容物と袋を引き出します。
傷が小さく済みやすいため、術後の痛みや腫れが少なく、回復も早いのが特徴です。
おしりのように摩擦が起こりやすい場所でも、なるべく負担をかけずに治療したい方に向いています。
切開法

切開法は、粉瘤を袋ごと確実に取り除くための基本的な手術方法です。
皮膚を切開して中の内容物と袋(嚢胞)を丁寧に取り出すため、再発のリスクを最も低く抑えられるのが大きなメリットです。
この方法は、粉瘤が大きい場合や、炎症や感染がスで選ばれています。
くりぬき法より傷はやや大きくなりますが、確実に治したい方や再発を避けたい方に向いている術式です。
なお、くりぬき法・切開法どちらの手術も局所麻酔で行う日帰り手術で、術後はそのままご帰宅いただけます。
どちらが適しているかは、診察時に粉瘤の状態を見て医師がご案内します。
おしりの粉瘤の手術費用

粉瘤の手術は健康保険が適用されるため、自由診療ではありません。保険で3割or1割負担で済みます。
自己負担3割の方であれば、数千円~1万円台後半程度が一般的な費用の目安となります。
粉瘤の大きさや手術方法によって金額は変わるため、診察時に明確な費用をご案内しています。
おしりの粉瘤、術後はどう過ごす?

術後は、清潔を保ちつつ、過度な圧迫や摩擦を避けることが大切です。おしりはどうしても座る機会が多いため、術後数日は座り方に注意が必要となります。
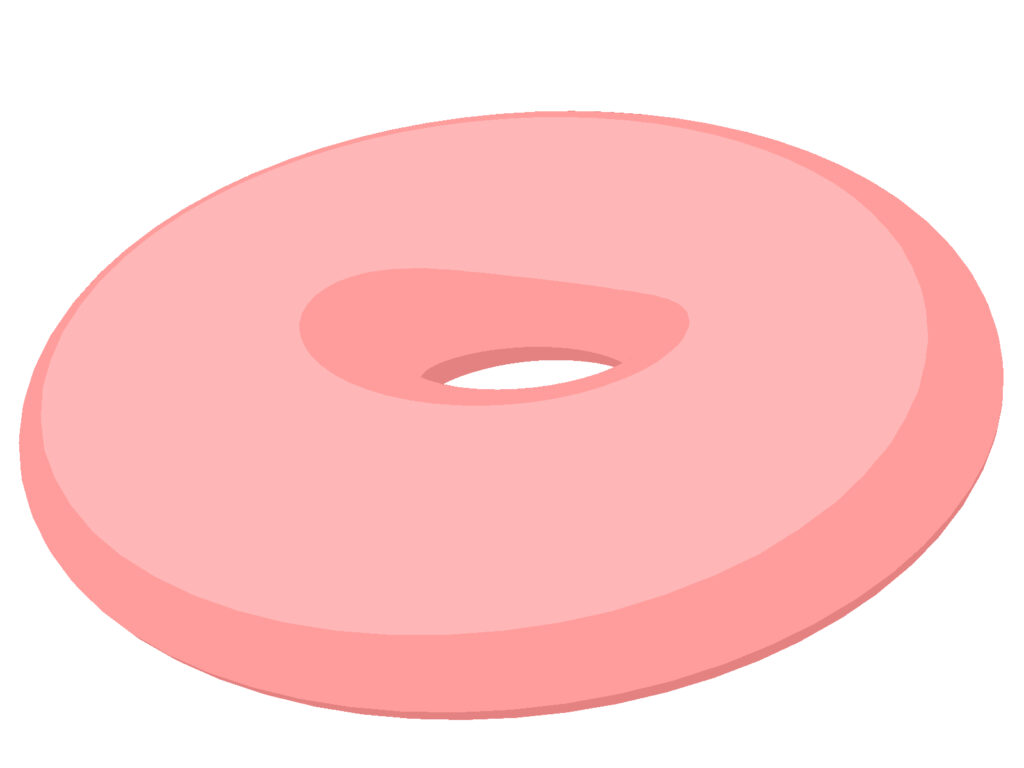
柔らかいクッションを使用したり、片側に重心をかけるなどの工夫が回復を助けます。

また、シャワーは当日から可能な場合もありますが、入浴や激しい運動は数日~1週間程度控えるように指示されることが多いです。術後の出血や感染を防ぐためにも、指示された処置方法を守り、必要に応じて経過観察にお越しください。

特におしりは再発リスクも高いため、術後も肌を清潔に保ち、摩擦や蒸れを減らす生活習慣を意識することが再発防止につながります。
おしりにできた粉瘤に寄せられるQ&A

Q. おしりの割れ目にできた粉瘤は何科を受診すればいい?
A. 軽症の場合皮膚科でも診察は可能ですが、根本的な治療(手術)を希望される場合は、形成外科や外科など、外科的処置に対応できる医療機関を受診するのが望ましいです。粉瘤専門クリニックであれば、より的確な対応が受けられます。
Q. 粉瘤がおしりにできたけど見せるのが恥ずかしいです。他にも同じく受診される方はいますか?
A. はい、とても多いです。おしりの粉瘤は誰にでも起こり得る皮膚疾患で、特に20~50代の男女に多く見られます。当院でも多数の方が受診されており、プライバシーに配慮した診察を行っていますので、どうぞご安心ください。
Q. おしりの粉瘤は再発しますか?
A. 手術で袋(嚢胞)を完全に取り除けていれば再発は少ないですが、部分的に残っていた場合や同じような生活習慣が続いている場合には、再発することもあります。再発リスクを減らすためにも、早期の適切な手術と術後の生活管理が大切です。
Q. おしりの粉瘤を自分で押し出したり潰してしまったら?
A. 自分で潰すのは絶対に避けてください。一時的に内容物が出ても袋が残っていれば再発しやすくなりますし、細菌が入ることで炎症や感染が悪化するリスクも高まります。痛みや膿が出ている場合も、速やかに医師の診察を受けてください。
まとめ
おしりにできる粉瘤は、座る・歩くといった日常動作に影響を与えるだけでなく、放置すれば炎症や感染のリスクもあるため、早期対応が重要です。見た目ではニキビや脂肪腫と間違えやすく、自己判断が難しいケースも多いため、気になる症状があれば早めの受診をおすすめします。
当院では、粉瘤の診断から日帰り手術、アフターケアまでを一貫して対応しており、おしりにできた粉瘤にも多数の治療実績があります。
プライバシーに配慮した環境で、安心してご相談いただけますので、「こんな場所にできて恥ずかしい」と思わず、お気軽にご来院ください。

 アクセス
アクセス



